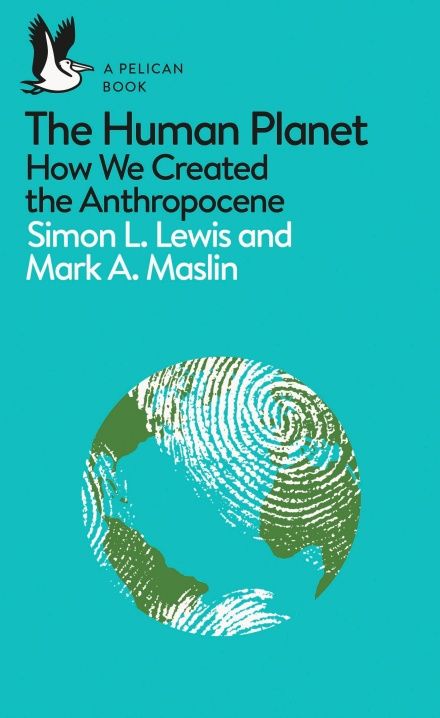인류세의 철학 (philosophy in the Anthropocene) – 사변적 실재론 이후 인간의 조건 / 시노하라 마사타케 / 섬기는 사람들 / 2022

인류세의 철학 저자 시노하라 마사키출판 섬기는 사람들 출간 2022.08.31.
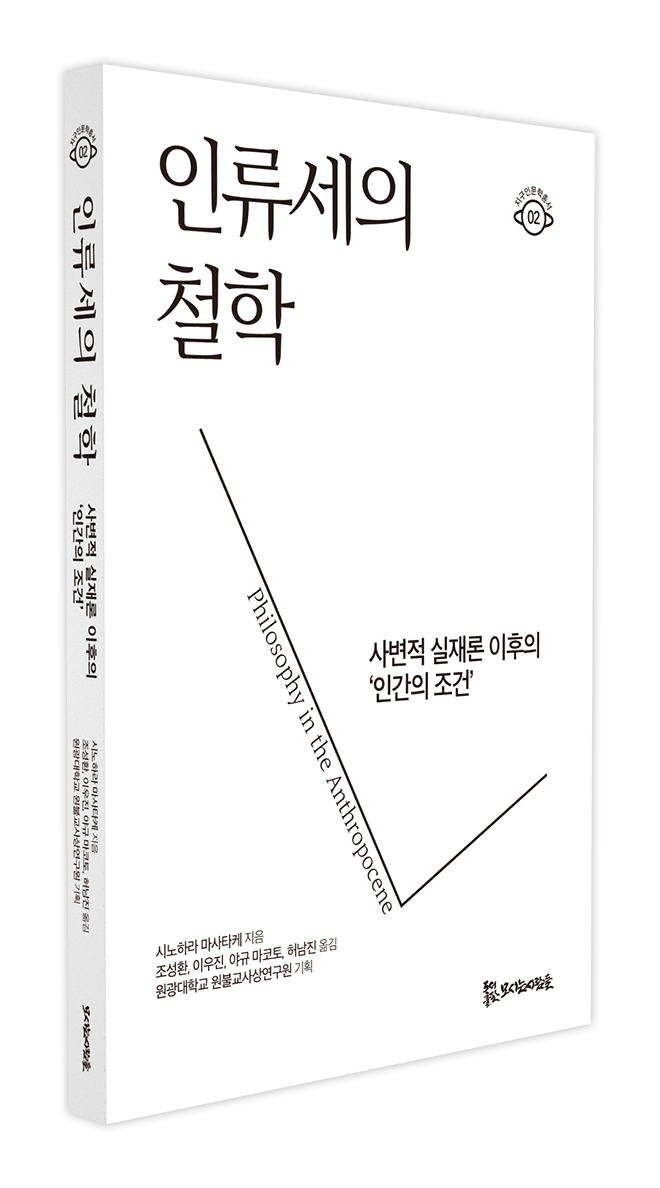
現在、地球上には温暖化、豪雨、海面上昇、パンデミックのように、「人間の条件」を考える前提を揺るがす事態が発生している。 それは「実存的危機(existential crisis)」とも言える。 人間世界に関する前提そのものの変化と更新が求められているからだ。 これまでは人間世界と自然環境の区分が固着化し、自然環境は統制可能な対象と見なされてきたが、このような近代的な想定が揺れている。 自然環境は安定した背景ではなく、人間世界のあり方を揺るがすものだと認識が変わりつつある。 ここで投げかけられる質問は「これに対応できる人文科学的思考は何か」そして「不安定な状況で生きるということはどんなことか」ということだ。私たちは人間と自然、自然と人為の問題をよく熟考してこそ人類税問題を解くことができる。 近代のように人間と自然を二分法的に見てはならず、だからといって以前のように自然をありのままに認めようというわけでもない。 (22p)人類税は2000年にオランダの大気化学者パウル·クリュチェンが使用して広く知られた概念であり、「事変的実在論」はフランスの哲学者クィンテン·メイヤスが2006年に書いた「有限性以後」に登場する用語だ。 「人間の条件」はドイツの政治哲学者ハンナ·アーレントが1958年に書いた著書タイトルだ。 それでこの本の題名が意味するところは「人類世時代の人間の条件を事変的実在論という哲学的観点で考え直す」となる。 (23p)人類勢とはチャクラバルティの表現を借りれば、「産業革命以来の人間の活動で人間と自然の境界が崩壊し、それによって人間の条件が脅かされる時代」に要約できる。 ここで「人間の条件」は「人間の生活を支えてくれるものを意味する。 (24p)宇宙と地球、そして人間でない生命体は人間が存在することとは関係なく、人間とはかけ離れたところで、人間化されていないところで独立している。 (40p)人間の条件とは人間の活動を支え、成立させることであるが、アーレントはこれを人間の内面性とは独立した世界、すなわち事物性のある世界と考えようとした。 (42p)アーレントは近代以降の人間生活の問題を「人間の条件が自然から分離してしまった問題」と考えようとした。 『人間の条件』第2版(1998)に載せられた序文でマーガレット·キャノバン(Margaret Canovan, 1939~2018)はアーレントが人間の領域である公的世界に対する考察を地球という惑星、すなわち自然との関係の中で考えようとしたと述べている。 アーレントは1957年の人工衛星打ち上げを人類歴史上画期的な事件と把握したが、その理由は「人間が地球から抜け出す」という事実を意味するためだった。 すなわち「地球から空に逃げ出し、核技術のような実験を通じて人間の存在は自然の限界に挑戦していくことになる」ということだ。 アーレントは人間の領域が地球から離脱し、それ自体で自足する兆候を人工衛星の打ち上げで感知した。 (42p)人間生活は、それが何かをすることに活発に関係する限り、常に多数の人間と彼らが作り出す事物世界に根差している。 人間生活はその世界を離れることもなく超越することもない。 (43p)過去3世紀の間に人間が地球的環境に及ぼした影響力が増加した。 二酸化炭素を排出してきたため、地球の気候は今後数千年続いた自然な運行からとんでもないほど逸脱していくだろう。 現在多くの点で人間が優位にある地質学的時代に「人類税(Anthropocene)」という言葉は適切だと考えられる。 それはこれまで10,000年や12,000年続いた温暖な時代であるホロセー(Holocene)に取って代わる。 (44p)アーレント(Hannah Arendt 1906-1975ドイツ出身のホロコースト生存者)によると、人間は自然な地球に住んでいるだけでなく、人間が作り出す世界(man-made world)に住まない限り、完全に人間にはなれない。 (49p)ベンヤミン(Walter Benjamin 1892-1940)は霊性や神聖さという意味でのオーラについて次のように述べている。いったい「アウラ」とは何か。 時間と空間で構成された神秘的な織物である。 つまり、いくら近くにいても、ある遠距離が一回的に現れるのだ。 夏の日の午後に静かに休みながら地平線の上に続いた山々を、あるいは木の下で休んでいる人の上に影を落としている木の枝を目で追うこと、これがこの神々のオーラを、この木の枝のオーラをホホホするのだ。 オーラという霊的なものは、遠くで維持される一回性的な、つまり他のものとは交換できない唯一のものとして現れるのだ。 (68p)自然を人間から分離させ、神秘化した対象として理解するのではなく、「取り巻くもの」と捉えること、人間を含む様々なものを関連付けて存在させる「取り巻くもの」の領域として概念化することである。 (75p)環境は事件が起きるここがある空間であり、密度があり具現化されているため緊張の程度が高まっている。 それは完全に満たされているわけでもなく、空虚なものでもない。 そこには潜在性の感覚が、何か「今からでも」起き上がろうとする感覚があるが、これにふさわしい用語や概念はまだ存在しない。 (79p)自然は人工世界を老化させ衰退させることで、それを絶えず脅かす。 これを通じて自然は人工世界にも自分の存在感を感じさせる。 (87p)人間生活の条件が脆弱なのはなぜか? それは人間生活の条件が人間的な意図の産物という意味での人工空間だけでは完結できず、生活を営む人々を囲んで支えてくれる自然と出会うところで形成されるためだ。 モートンが「事物には奇妙なところがある。」と主張したのは人工と自然が隠密に出会うところに事物が存在するという事実を直観していたためだ。 しかし、日常的な人間生活では、物事の奇妙さを概して意識していない。 人間が作り出す世界に生きることに慣れるにつれて、それ以外の世界、すなわち人間が作り出すものとは無関係に存在する世界はアーレントが言う「世界ではないもの」と認識され、そこで感覚が閉じられ思考も止まるからだ。 (90-91p)惑星の温暖化が脅かしているのは地質学的な惑星そのものではなく、ホロセーの時期に発展した人間生活の生存が依存する生物学的で地質学的な条件そのものだ。 (98p)アーレントは人間の生活を3つのレベルで考える。第一に、人間の世界である。 複数の人間が行為して対話する中で形成される現れる空間だ。第二に、物事の世界である。 人間世界との関連の中で形成される世界である。 したがって、人間活動と関係のない大地そのもの、河川そのものとは区別される。物事の世界は、それを形成した人間よりも長い間続く。 この長い間続く性質をアーレントは類型性や物想性、世界性といった言葉で表現している。 彼女の議論が重要なのは、このような性質が自然に存在するのではなく、人間が実際に作っていく活動とともに生じると主張するためだ。第三に、世界そのものである。 人類勢の問題設定を考慮してみると、世界そのものとは人間世界と事物体系が形成されるより先んじた地球、惑星そのものを意味する。 惑星としての世界そのものに事物の世界が積もり、そこに人間の世界-間主観的に共有される意味の世界、虚構的な世界-が形成されていく。ここに提示された見解を人類勢の問題設定と関連付けて読み上げることが本書の課題である。 (101-102p)世界に対する私たちの経験方式を恒久的に変え、新しく物事を見る視覚を、新しい悲しみの方式を、探さなければならない。つまり人間の条件が崩壊し始めているということだ。 問題は私たちが経験する方式、物の見方、悲しむ方式が人間の条件の崩壊以前の状況と同じであるため、出てくる議論も展開される思考もすでに始まっている新しい事態に対応できないという点だ。 (112p)人間はただ存在するのではなく、自分が存在することを知っている。 十分な自覚状態で自分たちの世界を研究し、それを自分の目的に合わせるために変化させる。 人間は「自然の因果性(natural causation)」に干渉する方法を学んだ。 (115p)チャクラバルティは、気候変動とともに起こる事態をめぐる思惟を広げていくことを、ヤスパースの「前代未聞の事態に対する意識」に関する検討から始めた。 その理由は、技術化が人間生活の条件を根本的に変化させた現実は、専門的に分化した個別知識の枠に留まっては事由できない問題だと見たためだ。 ひいては人間が地球から分離することで根のない草のような生活圏を形成しているという自覚を促し、その結果に対する理由が何よりも重要だということを話すためだった。 (127p)人間の生存条件は人間化されず人間の接近を越えるところにあるが、人間の生存を現実的に後押ししてくれるため、単に役に立たず乱雑な事物の蓄積として片付けることはできない。 物事は「有用か無用か」という人間が定めた枠組みを離れたところでただ存在している。 物事を見て「舞踊」や「廃棄物」と考える人は依然として有用、舞踊の枠組みにとらわれているからだ。 (134p)人間が自然のあり方を変えているという意識が高まっている。 二酸化炭素排出量の増加が温暖化を引き起こすという主張に対しては依然として否定的な反応もあるが、ダム建設によって堆積した土砂、都市建設で使用されたプラスチックやアルミニウムといった物質の堆積物のように、物質的次元で明らかに現れるものもある。 これらの事物の集積が自然界にどのような影響を及ぼすのか。 ひいては人間世界のあり方をどのように変えるのか。 人間が自然を変化させることをどう考えるべきか。 これらの質問をめぐる考察は始まったばかりだ。 (137p)アーレントは人間の条件を事物性があると見た。 そして物事を二つの状態に区分した。 一つは人間的世界の構成要素になった状態であり、もう一つはその外に追い出され互いに無関係なものが堆積している状態だ。